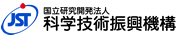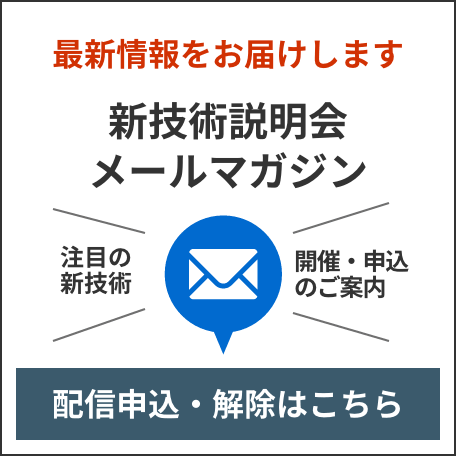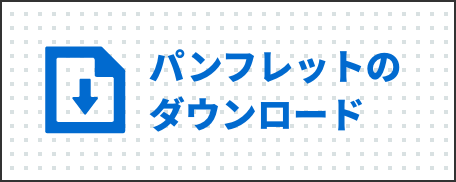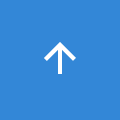名古屋工業大学 新技術説明会
日時:2008年10月17日(金)
会場:科学技術振興機構 JSTホール(東京・市ヶ谷)
参加費:無料
発表内容一覧
発表内容詳細
- 通信
1)ディジタル通信における高度な変調方式による高機能化
名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 准教授 岡本 英二
新技術の概要
ディジタル通信において、通常上位レイヤで行われている適応伝送や暗号化を、物理レイヤにおいて変調方式の高度化により比較的簡易に実現し、且つ通信路符号化利得の向上を得ることが可能な方法を開発した。
従来技術・競合技術との比較
従来変調方式と符号化の組み合わせを変更する適応伝送や、秘匿性を高める暗号化は上位レイヤで行われていたため、全体的な伝送効率の低下を招いていた。本手法はこれを変調方式の高度化により効率的に実現する。
新技術の特徴
・物理レイヤにおける符号化変調方式により異なる伝送速度や符号化の強さをもつマルチモード伝送を行うこと
・移動通信におけるマルチパス干渉をターボ等化と呼ばれる手法により取り除くことができること
・物理レイヤにおける符号化変調方式により秘匿性の高い通信を実現できること
想定される用途
・ディジタル無線通信の送受信装置
・移動無線通信時の伝送の効率化向上のために送受信装置
・簡易な秘匿性通信実現のために送受信装置
- 情報
2)高分解能を実現するパルス幅変調方式とその制御方法
名古屋工業大学 大学院工学研究科 創成シミュレーション工学専攻 准教授 米谷 昭彦
新技術の概要
デジタル回路によるパルス幅変調において、パルスの幅だけでなくパルスの位置も変化させることにより、出力波形のバリエーションを増やし分解能を向上させる。フルデジタル・オーディオアンプの性能向上に寄与する。
従来技術・競合技術との比較
従来はデジタル回路によるパルス幅変調の分解能は、パルス周波数とクロック周波数の比によって決まってしまっていた。このことが、フルデジタル・オーディオアンプの性能を制限する一要因になっていた。
新技術の特徴
・パルス幅変調の分解能を向上。
・高分解能を実現させるためのノイズ・シェーピング技術も提供。
想定される用途
・フルデジタル・オーディオアンプ。
・その他、単相パルス幅変調を用いる機器。
- 情報
3)時空間解析に基づく分散型ファイアウォール診断技術
名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 教授 高橋 直久
新技術の概要
分散配置された複数ファイアウォールのIPパケットフィルタに対して、フィルタの時間的関係と空間的関係を解析し、ネットワーク管理者の意図しない誤った設定、互いに矛盾のある設定、冗長な設定を検出する。
従来技術・競合技術との比較
時空間解析技術を開発し従来技術の以下の問題を解決した。(1)ファイアウォールの設定が時間とともに変動する場合に適用できない。(2)複数フィルタの組合せに起因する複合的な設定異常に対応できない。
新技術の特徴
・空間的解析により、特定の複数フィルタの組み合わせにより生じる矛盾や冗長などの設定異常を検出
・時間的解析により、指定された期間だけ特定のポートを開けるなどの時限付きフィルタの実行制御と誤り検出を実現
・時空間的解析により、ステートフルファイアウォールの設定異常を検出
想定される用途
・ファイアウォールの設定変更時に用いる妥当性検査ツール
・ネットワークの構成変更時に用いる設定変更ツール
・セキュリティポリシーとファイアウォールの整合性検査ツール
- エネルギー
4)新規溶解性フラーレン誘導体を用いた有機薄膜太陽電池材料
名古屋工業大学 大学院工学研究科 未来材料創成工学専攻 准教授 林 靖彦
新技術の概要
高分子有機太陽電池の発電層に、一般的に用いられるC60の誘導体PCBMに代わり、溶解性が高く高い電子受容能力をもつn型フラーレン誘導体を新規に開発した。新規材料は、有機太陽電池のn型材料として期待される。
従来技術・競合技術との比較
高分子系有機太陽電池の発電層として、一般に、ポリ(アルキルチオフェン)とC60の誘導体PCBMの組み合わせが広く使われている。PCBM以外のC60の誘導体の合成が模索されているが、未だPCBMを凌ぐ有機太陽電池用n型材料は開発されていない。
新技術の特徴
・新規溶解性フラーレン誘導体
・高い電子受容能力
・新構造有機薄膜太陽電池
想定される用途
・有機薄膜太陽電池
・有機電界効果トランジスタ
- エネルギー
5)マイクロ燃料電池用の廉価な水素供給体の開発
名古屋工業大学 大学院工学研究科 物質工学専攻 教授 林 昭二
新技術の概要
燃料電池の水素供給体として鉄媒体があり、4.8mass%の水素を発生し、発熱を伴うので全エネルギー効率に優れるが、焼結が問題である。本技術は、鉄の表面に硫黄を吸着させ焼結を防止することにより、廉価な水素供給体を作る新技術である。
従来技術・競合技術との比較
従来の焼結防止技術は、酸化鉄表面に異種酸化膜を作る方法であり、還元ガスに水素ガスのみ使用するために高価で大量生産ができないという欠点があった。本技術は微量硫黄含有還元ガスが利用でき、廉価で大量生産に向くという利点がある。
新技術の特徴
・多量鉄含有廃棄物に基づく廉価な酸化鉄微粒子が出発原料であり、廉価な微量硫黄含有還元ガスが利用可のため大量生産向き。
・鉄媒体は、酸化反応において約300℃で水蒸気をほぼ100%の高効率で水素に変換させる利点を有する。
・酸化鉄の還元酸化サイクル反応が高効率で繰返し可能のため再生使用性に優れるため、更に廉価な水素供給体として期待できる。
想定される用途
・モバイル用のマイクロ燃料電池への水素供給体
・自動車に搭載する燃料電池への水素供給体
・家庭や事業系用などの燃料電池(コジェネ型)への水素供給体
- エネルギー
6)低・中温型無加湿燃料電池用プロトン伝導性ハイブリッド材料
名古屋工業大学 大学院工学研究科 未来材料創成工学専攻 教授 春日 敏宏
新技術の概要
低・中温域、無加湿で高いプロトン伝導性を示し、長期安定性、成形性に優れる、新しい有機無機ハイブリッド材料と、これを極めて容易に安価に合成できる方法を開発した。
従来技術・競合技術との比較
固体高分子膜、リン酸水和物などの無機結晶、非晶質ゲルなどは、耐熱性に乏しく100℃以上では使用できない。リン酸型燃料電池では、リン酸の揮発の問題がある。本技術はこれらの問題を解決するもので、周辺設備のスリム化も期待できる。
新技術の特徴
・無加湿中温域でも高プロトン伝導性と熱安定性を確保できる。
・150~200℃までほとんど熱変化がない。吸湿性もほとんどない。
・自立膜化が可能な柔軟性のある材料で、安価に製造できる。
想定される用途
・中温型燃料電池用電解質、および電極用添加剤
お問い合わせ
連携・ライセンスについて
名古屋工業大学 産学官連携センター 企画・管理部門
TEL:052-735-5627FAX:052-735-5542Mail:office
 tic.nitech.ac.jp
tic.nitech.ac.jp URL:http://www.tic.nitech.ac.jp/
新技術説明会について
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町
TEL:03-5214-7519
Mail:scett jst.go.jp
jst.go.jp