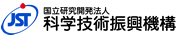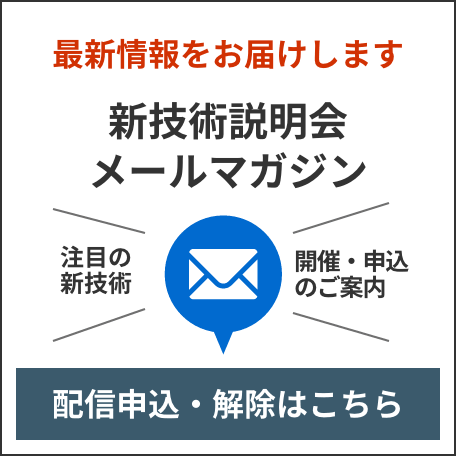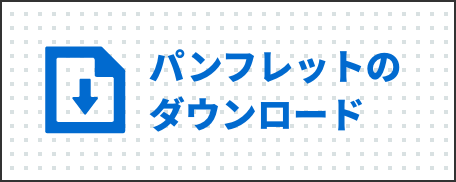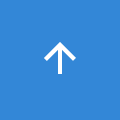先端的低炭素化技術開発(ALCA) 新技術説明会 ~バイオ分野~
日時:2015年02月17日(火)
会場:JST東京本部別館ホール(東京・市ヶ谷)
参加費:無料
発表内容一覧
発表内容詳細
- 環境
1)転写因子による木質バイオエンジニアリング
産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 植物機能制御研究グループ 主任研究員 光田 展隆
新技術の概要
道管以外で木質を形成しない変異体に様々な転写因子を発現させる手法により、新しい形質を持った木質を再構成させています。現在までに、木質形成が大幅に強化された植物や、これまでにない組成の木質を持った植物などを作成することに成功しています。
従来技術・競合技術との比較
従来、植物の改変は野生株をベースに行われてきたが、本研究では木質を形成しない変異体をベースにしているのでこれまでにない画期的な木質を持つ植物を作出することができる。
新技術の特徴
・木質の生産性や強度を大きく向上させることができる
・オーダーメード木質を作らせることができる
・技術開発の副産物として、10種類の還元糖を高速に定量する技術を開発した
想定される用途
・パルプ原料木の生産性向上
・バイオリファイナリー原料植物の効率化
・食品や木質中の糖組成の分析
関連情報
・サンプルの提供可能
- 環境
2)酵素クラスター効果による水に不溶な原料の効率的分解技術
東北大学 大学院工学研究科 バイオ工学専攻 教授 梅津 光央
新技術の概要
50nmを切るナノ粒子表面に酵素を高密度に固定化させることによって、セルロースなどの水に不溶な固相基質を効率よく分解することができる技術。
従来技術・競合技術との比較
酵素の安定化のためだけの固定化ではなく、酵素活性を飛躍的に向上させる技術。特に、水に不溶な固相基質を効率よく分解することに実績がある。
新技術の特徴
・固相基質を分解する酵素の機能を飛躍的に向上させる技術
・ナノ素材を酵素の触媒機能を向上させることに利用
・既存の酵素液の濃度を減少させずに新たな酵素を添加可能
想定される用途
・バイオマス・食物中のセルロースの糖化
・数種類の酵素を使った化学反応の効率化
関連情報
・場合によっては試作可能
- アグリ・バイオ
3)水生植物の成長を加速する微生物:廃水を肥料とするバイオマス生産を目指して
北海道大学 大学院地球環境科学研究院 環境生物科学部門 教授 森川 正章
新技術の概要
ウキクサをはじめとする水生植物は汚れた水を栄養として生育できるため、省エネ型の水処理技術として有効です。さらに、そこから収穫される植物は、タンパク質やデンプンが豊富なバイオマス資源として利用できます。私たちは世界に先駆けてウキクサの成長を約2倍加速する微生物や有害物質を分解する微生物を多数発見しました。このような微生物群と植物の共生システムを合理的にデザインすることで、格段に効率の高い水処理と資源生産を実現します。
従来技術・競合技術との比較
従来の水処理技術として活性汚泥処理法が主流ですが、曝気などの所要電力量は大きく余剰汚泥の処理も問題となっています。これに対して水生植物を利用した水処理技術は広い敷地を必要としますが、光エネルギーに依存するため省エネ効果が期待できると同時に植物バイオマスを生産することができます。従って、東南アジアあるいは中国などの食品系工場廃水あるいは富栄養汚染湖沼の水処理技術として最適です。一方、藻類バイオマス生産技術と比べた場合、生産物の回収が容易であることが有利な点です。
新技術の特徴
・新規生理活性物質
・光利用技術
・ビオトープ
想定される用途
・省エネ型水処理技術
・石油代替化成品原料&家畜飼料生産技術
・植物工場の省エネ化
- アグリ・バイオ
4)珪藻に有用物質を高い効率で生産させるための新しい遺伝子導入方法
兵庫県立大学 大学院生命理学研究科 生命科学専攻 准教授 菓子野 康浩
新技術の概要
海洋性中心目珪藻ツノケイソウに外来遺伝子を導入して、本来珪藻が作ることができない物質を生産させるための技術を開発した。この技術により、大気中二酸化炭素と太陽光による光合成で、有用で付加価値の高い代謝物質を効率的に生産するバイオファクトリー構築が可能となる。
従来技術・競合技術との比較
従来、ツノケイソウに外来遺伝子を導入して発現させることは不可能であった。少数の他種微細藻類では類似の手法があるものの、藻類の増殖特性、環境適応性等を考慮すると、バイオファクトリーのプラットフォームとして抜きんでている。
新技術の特徴
・化学物質の素材生産
・サプリメント
・医薬品
想定される用途
・本来珪藻が合成可能なカロテノイド、油脂等の代謝産物を、太陽光を使って低コストで大量生産する(合成能力を高める)。
・少数の生物のみが生産することが可能で、有用な物質を作る酵素の遺伝子を導入し、そのような物質を太陽光を使って低コストで効率的に生産する。
・他種生物での生産実績があるがコストがかかる物質の生産系を移植し、太陽光を使って低コストで効率的に生産する。
- アグリ・バイオ
5)タンパク質を配列・配置する技術(1)
九州大学 大学院工学研究院 応用化学部門 教授 神谷 典穂
新技術の概要
特異な形をしたビオチン分子で機能性タンパク質を部位特異的にラベルし、多価のビオチン結合部位を有するアビジンと水溶液中で混合するだけで、1次元状にタンパク質を配列化させる技術を開発しました。
従来技術・競合技術との比較
酵素反応を利用するタンパク質の部位特異的なビオチン化と、ビオチン化基質の分子設計により、広く用いられているアビジンービオチン相互作用を介して、従来法では困難なタンパク質の1次元配列化に成功しました。
新技術の特徴
・機能性小分子ラベルによるタンパク質機能の高付加価値化
・機能を有するタンパク質ポリマーの形成
・化学的手法を必要としないタンパク質固定化法
想定される用途
・異なる酵素の連携による共奏触媒系の構築
・新規バイオマス分解酵素触媒系の構築
・タンパク質の1次元集積によるバイオ医薬関連試薬としての利用
- アグリ・バイオ
6)タンパク質を配列・配置する技術(2)
九州大学 大学院工学研究院 応用化学部門 教授 神谷 典穂
新技術の概要
生体内で還元反応を触媒する酵素を足場(scaffold)として、これに抗体結合機能を有するタンパク質と、金に対する親和性を有するペプチドを融合することで、目的タンパク質が自動的に金ナノ粒子上に配置される技術を開発しました。
従来技術・競合技術との比較
安価な基質を使ってNADHを生成する酸化還元酵素反応を利用する金ナノ粒子の調製と、融合タンパク質の分子設計により、広く用いられている金ナノ粒子上に目的タンパク質が自発的に提示される系の構築に成功しました。
新技術の特徴
・機能性小分子ラベルによるタンパク質機能の高付加価値化
・機能を有するタンパク質ポリマーの形成
・化学的手法を必要としないタンパク質固定化法
想定される用途
・イムノクロマト等その場検出におけるプローブ材料
・抗体の集積による抗原検出試薬としての利用
・ナノ粒子上へのタンパク質集積によるバイオ医薬関連試薬としての利用
関連情報
・組換え酵素遺伝子を提供可能
- アグリ・バイオ
7)発酵微生物の耐熱化及び堅牢化と高温・ロバスト発酵系の開発
山口大学 中高温微生物研究センター 教授(特命) 松下 一信
新技術の概要
通常の微生物発酵には冷却が必須であり,コスト増の要因になっている。加えて,いくつかの変異を有する脆弱な発酵生産菌では,特にその冷却や生産管理が必須である。それ故,耐熱化育種し、堅牢化した発酵微生物を利用する高温・ロバスト発酵系の開発は有用である.
従来技術・競合技術との比較
「耐熱化」株を用いると、従来のような温度管理が必要のない「非温度制御発酵」や滅菌操作の軽減が可能となる。加えて、菌株の堅牢化が期待され、連続発酵や易管理発酵が可能となり、経費のさらなる削減も期待される。
新技術の特徴
・非温度制御発酵
・発酵コストの削減
・滅菌操作の軽減・簡易発酵槽の利用
想定される用途
・バイオエタノール生産
・アミノ酸・酢酸発酵
・その他医薬中間体生産
- アグリ・バイオ
8)バイオプロピレン生産を目指したプロパノール発酵技術の開発
大阪府立大学 大学院生命環境科学研究科 応用生命科学専攻 教授 片岡 道彦
新技術の概要
プロピレンをバイオマスから生産することができれば二酸化炭素の排出量を削減することができます。その前駆物質となるプロパノールを糖類から効率よく生産する新規発酵プロセスの開発を進めています。
従来技術・競合技術との比較
すでに開発されているプロパノール発酵技術と比較すると、対糖収率において約1.5~2倍の向上が見込まれます。また、バイオマス由来のポリプロピレンの二酸化炭素排出量は化石資源由来のものの半分以下になると試算されています。
新技術の特徴
・人工的に新しく設計した生合成経路構築によるプロパノール生産
・対糖収率の高いプロパノール発酵生産
・バイオマスを原料とするプロパノール発酵生産
想定される用途
・バイオマスからのプロピレン・ポリプロピレン生産
・バイオマス由来の燃料添加剤
・バイオマス由来の多目的有機溶媒
- 環境
9)新規酵母株を用いたバイオマスからの油脂の一貫分泌生産
龍谷大学 法学部及び農学研究所 教授 島 純
新技術の概要
生物油脂は、バイオディーゼル等の燃料や化学原料として有用であるが、細胞内からの油脂の抽出は煩雑かつ高コストであり、産業利用のボトルネックとなっていた。本技術開発では、探索研究を行い、油脂の高生産能を有し、さらに全油脂の約4割を細胞外分泌する油糧酵母株を見いだした。生産される油脂はオレイン酸が中心であり、バイオ燃料や化学工業原料として利用可能である。また、本菌株は、多様な糖の資化性を有しており、未利用バイオマスや廃棄物等から油脂の一貫分泌生産への応用可能性が極めて高い。
従来技術・競合技術との比較
油脂を分泌生産することが可能であることから、煩雑な細胞からの油脂抽出プロセスを簡略化することが可能である。また、多様な炭素源資化性を有しており、未利用バイオマス資源からの油脂生産が可能となる。
新技術の特徴
・生物油脂の分泌生産
・バイオマスからの油脂の一貫生産
・化石燃料の代替
想定される用途
・バイオ燃料生産
・化学工業原料
・廃棄物の有効利用
- アグリ・バイオ
10)微生物由来の透明スーパーエンプラおよびその炭素繊維複合材料
北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 マテリアルサイエンス専攻 准教授 金子 達雄
新技術の概要
遺伝子組換え菌から生産した芳香族アミンを出発物質として極めて高い熱力学性能、透明性、高絶縁破壊電圧を示すポリイミドフィルムおよびアラミドフィルムを開発し、かつこれらのフィルムの炭素繊維複合体を開発した
従来技術・競合技術との比較
従来は透明性の高い非結晶性プラスチックフィルムの性能は低いのが問題点であり、電子ペーパーなどへの応用の足かせとなっていたが、今回微生物を用いた新たな分子設計により透明かつ高い熱力学性能、高い絶縁破壊電圧を示すバイオ由来フィルムを開発した。
新技術の特徴
・透明かつフレキシブルな高性能絶縁フィルム
・透明かつ高力学性能を持つ成形体
・透明なマトリックスを持つ炭素繊維複合材
想定される用途
・電子ペーパー部材
・LED封止剤、その他ガラス代替
・輸送機器ボディ
関連情報
・NDA締結のもとで試作可能
・展示品あり(透明フィルム片)
・外国出願特許あり
お問い合わせ
連携・ライセンスについて
科学技術振興機構 環境エネルギー研究開発推進部 低炭素担当
TEL:03-3512-3543FAX:03-3512-3533Mail:alca
 jst.go.jp
jst.go.jpURL:http://www.jst.go.jp/alca/
新技術説明会について
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町
TEL:03-5214-7519
Mail:scett jst.go.jp
jst.go.jp