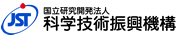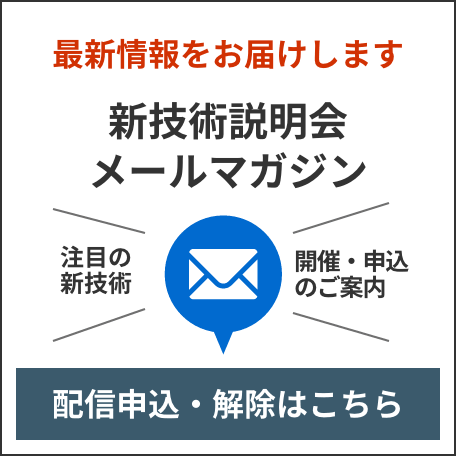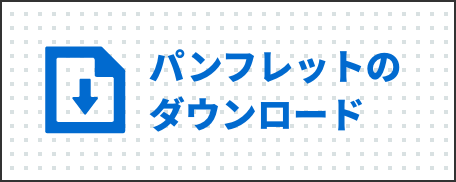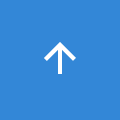JST知的財産戦略センター 新技術説明会 <新技術概要【当日資料PDFあり】>
日時:2015年12月08日(火) 10:30~15:45
会場:JST東京本部別館1Fホール(東京・市ケ谷)
参加費:無料
発表内容一覧
発表内容詳細
- アグリ・バイオ
1)様々な培養基材表面で均一な細胞凝集塊を大量に形成させるためのマスクシート
東京大学 先端科学技術研究センター 医用マイクロマシン講座 講師 池内 真志
新技術の概要
表面を親水化した樹脂シートに、直径100μm程度の貫通孔を多数形成する。貫通孔の上面には傾斜が設けられ、水平面が全く存在しない。このマスクシートを様々な培養基材表面に置き、細胞を播種すると、細胞は各孔に均等に分配された後、親水化した壁面には接着できないため、自発的に凝集し、均一な塊が大量に形成される。
従来技術・競合技術との比較
従来の細胞凝集塊を形成する培養基材はマイクロウェルが一体成型されているため素材が限定されるのに対し、本マスクシートを用いれば、任意の基材と組み合せて均一な凝集塊を大量に作製できるため、使用する細胞や目的に応じて、多様な使い方ができる。また、製品ラインアップを容易に増やすことができる。
新技術の特徴
・懸濁液を滴下するだけで、任意の基板上に、微粒子を簡便にパターニングできる。
・微粒子の分布形状、および分布密度を一度の操作で複数条件作製できる。
・生体に安全な基材であるので、例えば皮膚等に微粒子をパターニングすることもできる。
想定される用途
・スクリーニングモデルとしてのがん細胞凝集塊の大量作製
・幹細胞の均一な胚様体形成による分化誘導の効率化
・電極基板との組み合せによる脳モデル,心筋モデルの培養・解析
関連情報
・外国出願特許あり
・サンプルの提供可能
・展示品あり
- アグリ・バイオ
2)定量的PCR法によるHIV潜伏感染細胞の検出と病態把握法
微生物化学研究会 微生物化学研究所 第3生物活性研究部 研究員 水谷 壮利
新技術の概要
本方法は定量的PCR法を基にしたHIV残存感染細胞の挙動を把握する方法であり、治療により血中ウイルス量が検出限界以下となった場合においても体内に残存する感染細胞のウイルス由来RNAを測定することが可能である。HIV患者の新たな治療評価系バイオマーカーとして期待される。
従来技術・競合技術との比較
本方法は転写初期段階に短く停止するHIV由来のRNAを標的とした1ステップのPCR法によりHIV残存感染細胞の検出を可能とする。既存の方法は転写伸張後のウイルスRNAを検出する方法であり、血液量を多く必要とする点、Nested PCRである点などの煩雑性とその検出感度に問題が指摘されており、本方法はそれを解決する。
新技術の特徴
・潜伏感染ウイルス(肝炎ウイルス、EBウイルスなど)の感染細胞検出系への応用
・実験機器を選ばずできる定量的PCR法
・ウイルスRNAの検出系でありながら患者の免疫活性化状態を評価可能
想定される用途
・抗HIV薬による治療効果の感染細胞レベルでの評価法
・抗HIV薬治療を受けているHIV患者の免疫病態の評価法
・残存感染細胞の鎮静もしくは除去を目指した新規治療法の開発への評価系
関連情報
・外国出願特許あり
- アグリ・バイオ
3)スーパー抗体酵素の抗ウイルス・抗がん作用と応用展開
大分大学 工学部 客員教授 宇田 泰三
新技術の概要
抗体のように抗原を認識し、かつ、酵素的に分解できる高機能分子「スーパー抗体酵素」の性質と応用展開について説明する。特に、インフルエンザウイルスに対する「スーパー抗体酵素」と抗がん作用を有する「スーパー抗体酵素」について詳述する。
従来技術・競合技術との比較
抗体酵素はそれ自身が抗原を分解するのでADCC活性やCDC活性を必要としない事は従来技術には無い。また、従来の抗体と違って、生体外での使用が可能で、大気中のインフルエンザウイルスを直接撃退する手法の開発が可能である(共同研究チームを募集中)。
新技術の特徴
・予防分野
・医療分野
・健康分野
想定される用途
・インフルエンザの新予防法
・新型医薬品
・大気環境中のウイルス浄化
関連情報
・外国出願特許あり
- 情報
4)プログラム解析・検証ツールのマーケットシステムのための基盤技術
理化学研究所 計算科学研究機構 研究部門 利用高度化研究チーム チームリーダー 前田 俊行
新技術の概要
プログラム開発においてバグの発見・除去に有効なツールだが利用するのが困難だった「プログラム解析・検証」ツールを、利用者にとって使いやすく、かつ技術の提供者にとっても便利にするような方式・システム。
従来技術・競合技術との比較
従来の利用方法では、適切なプログラム解析ツールを選び、またインストールするのが容易でなく、またツールの実行に多くの計算機資源が必要となることがある等問題があったが、複数の利用者と複数のツールの提供者間でツールの登録・実行基盤を共有することで、この問題を解決する。
新技術の特徴
・複数の解析・検証ツールおよび複数の解析・検証対象プログラムを集積することにより、システムとして計算機資源を効率的に利用できる。
・複数の解析・検証ツールが集積されているため、利用者が適切なツールを選択・実行することが容易になる。
・複数の解析・検証対象プログラムが集積されているため、解析・検証ツールの開発者・研究者が自らのツールを試験することが容易になる。
想定される用途
・プログラム解析・検証ツールのマーケットシステムの提供
・プログラムの解析・検証環境の提供
・プログラム解析・検証ツールの研究・開発・テスト環境の提供
関連情報
・外国出願特許あり
- 情報
5)"流れ"のパターンを言語化し、流体設計を最適化する新アルゴリズム
京都大学 大学院理学研究科 数学教室 教授 坂上 貴之
新技術の概要
流体の実験や数値計算結果などから流線を抜き出したときに、それの流線の「かたち」に対して固有の文字列を与えることのできるアルゴリズム。膨大な流れの時間変化パターンから特徴的な構造を抜き出して簡単な文字列に表現することができるため流れを表現する共通言語になるだけでなく、その文字列を比較するだけで二つのパターンの間にどのような遷移が起こったかどうかを同定することができる。
従来技術・競合技術との比較
従来では実験や数値計算などの結果から得られた図や流れの様子だけからはわからなかった流れの構造が明確に抽出される。またそうした特徴的な構造と流体運動の様々な諸量との完全な対応づけを与えることで流れとそれが実現する機能のカタログ作成を容易にする。従来にはこのような技術はこれまでほとんど存在しないので、この技術を用いた新しい応用が生まれる可能性がある。
新技術の特徴
・計測や数値計算で得られた膨大な流れ場データから流線(とその変化)を抽出して、非常に小さな文字列(テキスト)データへと変換。
・文字列データだけからある流れ場から別の流れ場への遷移の経路が特定できるので、それを使って流れ場の最適化が可能になる。
・文字列は特定の流れ構造を表現するので、物体まわりの流れの構造が希望のものになるようにパターンの文字列を見ながら最適化できる。
想定される用途
・翼などの流体中の形状の最適設計(うまく渦を閉じ込めて効率的な揚力がえられるよう最適化)
・膨大な流れデータの(流線構造)の大幅な圧縮と統計解析(流れのビッグデータ解析)
・流れを特定する共通言語としてソフトウェアなどにその出力を組み込むことができる
関連情報
・外国出願特許あり
- 計測
6)細胞外物質を模倣して形成した“ナノスーツ”の表面保護効果
名古屋工業大学 大学院工学研究科 物質工学専攻 准教授 石井 大佑
新技術の概要
高真空環境下では、生物内の気体や液体が蒸発して死に至り、その微細構造は大きく変形する。一部の生物がもつ細胞外物質を電子線重合することで、高真空環境下でも生命維持可能なナノ保護膜(ナノスーツ)を発見した。さらに、細胞外物質の類似化合物で形成されたナノスーツを用い、生物の高真空環境下での生命維持を可能にした。このナノスーツの蒸発抑制能やガスバリア能に加え、酸化腐食防止能を明らかにしている。
従来技術・競合技術との比較
従来技術のプラズマ重合法では重合官能基が必要であり、水溶性の生体適合性物質はプラズマ照射により分解されるため、膜形成ができなかった。また、刺激により硬化する官能基をもたない生体適合性物質は硬化することができず、膜形成ができなかった。本特許に記載されているプラズマ照射条件を制御することで生体適合性物質中のCOOH基やOH基を重合に利用でき、一般的な重合官能基がない水溶性物質の架橋反応を進行させることに成功した。
新技術の特徴
・生体適合性物質(水溶性物質)膜形成が可能
・プラズマ照射条件により材料設計が可能
・複雑形状、大型、微小形状(ナノ)へも対応可能
想定される用途
・薬剤シート
・ドラッグデリバリーシステム用被膜
・建材・食品・皮膚等の表面保護膜
関連情報
・外国出願特許あり
・サンプルの提供可能(試作可能)
- 計測
7)NanoSuit法による生きたまま濡れたままの電子顕微鏡観察
浜松医科大学 医学部 総合人間科学(生物学) 教授 針山 孝彦
新技術の概要
生命科学研究では電子顕微鏡は欠くことのできない研究ツールとなっている。しかし、高真空に試料を曝さなくてはならないので、生物試料は事前に固定・乾燥・金属蒸着処理をしなくてはならず、処理による変形された死んだ状態を観察している。NanoSuit法では、生物試料表面に薄膜を形成させ、試料を生きたまま、濡れたまま電子顕微鏡観察を可能とした。
従来技術・競合技術との比較
1950年代から工夫を重ねてきた生物試料観察法では、乾燥標本を準備する必要から、事前処理として半日から数日必要である。また、観察試料は変形して、ありのままの生命の姿から遠いものを観察している。本技術は、数分間の処理で、ありのままの生命の姿を観察できる。
新技術の特徴
・試料を生きたまま濡れたままで電子顕微鏡観察する。
・リアルな構造を、高倍・高分解能で通常のSEMで観察可能。
・数分間のNanoSuit法処理時間で観察可能。
想定される用途
・基礎的生命科学研究
・医学や製薬などの応用生命科学
・迅速診断などの医学における治療
関連情報
・外国出願特許あり
- 計測
8)物質自身の発光をナノスケールで検出する顕微技術
東京大学 生産技術研究所 機械・生体系部門 准教授 梶原 優介
新技術の概要
本技術は世界最高感度のテラヘルツ(THz)波検出素子(CSIP:Charge Sensitive Infrared Phototransistor)を用いたTHz波顕微鏡に関する技術である。本CSIPを利用し、常温および低温(4.2K)における物質自身の発光(THz領域のエバネッセント波)をパッシブかつナノスケールで検出可能な顕微技術について紹介する。
従来技術・競合技術との比較
物質自身の発光(THz領域)をナノスケールで測定するためには外部照射光を利用せずにTHz波をパッシブかつ超高分解能で検出する必要があるが、技術的な問題のため、本顕微技術以外に実証例はない。
新技術の特徴
・外部照射光なしにナノスケール観測が可能。
・世界最高感度のTHz検出器を利用。
・ナノスケールの温度分布や電磁場分布の測定が可能。
想定される用途
・ナノサーモメトリー(ナノ温度計)
・バイオイメージング(細胞内の活性部分の可視化)
・グラフェン等新奇物質の新規物性評価
関連情報
・外国出願特許あり
- 計測
9)超音波で電気・磁気特性を評価する新しい非侵襲計測技術
東京農工大学 大学院工学研究院 先端物理工学部門 准教授 生嶋 健司
新技術の概要
超音波計測は医療診断や建築物構造検査などの非侵襲・非破壊測定として広く実用化されている。ところが従来方法では質量密度分布や弾性率分布といった力学的性質を反映するのみであり、物質および生体内の量子・電磁気特性の測定は困難である。 最近、我々は、超音波によって誘起される電磁応答を検出・画像化し、超音波による骨の圧電イメージングや鉄鋼材料の磁気イメージングに成功した。この計測方法は、現在、骨質診断やインフラ・鉄鋼における非破壊検査への実装を目指し開発をしている。
従来技術・競合技術との比較
従来の超音波計測は、硬い・柔らかい力学特性の違い、または質量密度のことなる異物を画像化することに用いられてきた。したがって、幾何学形状や傷・異物は可視化できてもその材質がどういう物性をもっている物かを評価することが困難であった。本発明により、物体内部の圧電特性や磁気特性を非破壊に評価することが可能となるため、超音波計測の全く新しい応用展開が期待される。
新技術の特徴
・生体内のコラーゲン線維組織(骨や腱など)や植物のセルロース線維組織の非侵襲評価
・強磁性体の非破壊・非接触評価(鉄鋼、ステンレス、磁性薄膜デバイスを含む)
・強化プラスチックなどの線維状プラスチックの非破壊評価
想定される用途
・骨の診断
・鉄鋼材の欠陥検査、ステンレス材の残留応力検査
・コンクリート内の鉄筋腐食検査
関連情報
・外国出願特許あり
- 計測
10)有機半導体などの固体のLUMO準位・電子親和力の精密測定装置
千葉大学 大学院融合科学研究科 ナノサイエンス専攻ナノ物性コース 教授 吉田 弘幸
新技術の概要
有機半導体のLUMO準位や電子親和力を固体・薄膜状態で調べる新しい実験手法の開発。有機EL素子や有機太陽電池などの有機半導体のLUMO準位を精密に決定できる唯一の研究手法であり、特にn型半導体、電子輸送材料の研究には欠かせない。
従来技術・競合技術との比較
従来の逆光電子分光法は、デバイス動作に近い条件で固体のLUMO準位・電子親和力が測定できる理想的な方法であるが、電子線による有機試料の損傷、光検出器の分解能が低い。代替法として、電気化学測定から求めた還元電位や、イオン化ポテンシャルに光吸収ギャップを足して求めた値が便宜的に使われているが、精度に問題がある。
新技術の特徴
・物質の空準位(LUMO準位)を固体・薄膜状態で測定。
・電子輸送材料、n型半導体の研究に不可欠。
・有機分子・生体分子でも試料のダメージがほとんどない。
想定される用途
・有機半導体のLUMO準位、電子親和力の精密測定
・有機分子・生体分子の空準位や電子親和力の測定
・固体物質の電子親和力測定
関連情報
・外国出願特許あり
・サンプルの提供可能(デモ測定可能(大学の共同研究規定に基づく))
お問い合わせ
連携・ライセンスについて
科学技術振興機構 知的財産戦略センター ライセンス担当
TEL:03-5214-8293Mail:license
 jst.go.jp
jst.go.jp新技術説明会について
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町
TEL:03-5214-7519
Mail:scett jst.go.jp
jst.go.jp