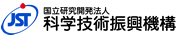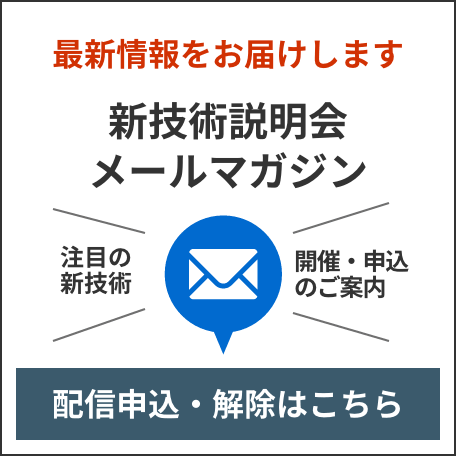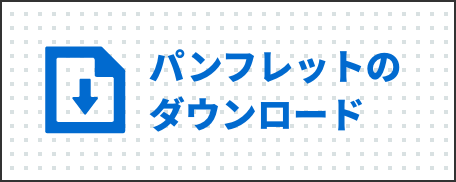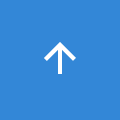広島大学 新技術説明会【オンライン開催】
日時:2025年10月23日(木) 13:30~15:55
会場:オンライン開催
参加費:無料
主催:科学技術振興機構、広島大学
発表内容一覧
発表内容詳細
- 13:30~13:55
- 製造技術
広島大学 大学院先進理工系科学研究科 教授 井上 克也
新技術の概要
編物の強靭性はその編物を構成する糸の素材に強く依存するが、利用可能な素材は編物の用途に応じて限定される。編物を構成する糸の素材ではなく、編物を構成する編み目等の構造の選択によって、編地の機械的強度を高めることができれば、素材が限定された場合でも編物の強靭性を高めることができる。本技術はトポロジー理論に基づいて編み目の構造を選択し、強靭性の高い編地を提供するものである。
従来技術・競合技術との比較
従来、編物の強靭性等の機械的性質について、編み目構造レベルでの研究が行われているが、編物の機械的性質に係るメカニズムについては十分に理解されていない。
新技術の特徴
・編物を構成する編み目等の構造の選択によって、編地の機械的強度を高めることができる
想定される用途
・安全・安心社会への貢献(防弾チョッキ・防刃ベスト・消防服・作業着等)
・輸送・モビリティ分野(材料の軽量化・タイヤ・シートベルト等)
・環境・持続可能性(リサイクル材料の高強度化・長寿命の布地等)
- 14:00~14:25
- アグリ・バイオ
広島大学 両生類研究センター 准教授 井川 武
新技術の概要
本技術は、特定の藍藻による動物の暑熱耐性誘導に関するものである。当該藍藻を含む飲食品組成物摂食により、動物の体温を摂餌に至適な範囲に調整可能である。結果、高温化であっても動物の食欲は維持され得る。本技術は、当該藍藻の体温調節機能を利用した、ヒトおよび畜産・愛玩動物等に暑熱耐性を付与する技術である。
従来技術・競合技術との比較
近年の夏場の高温による畜産動物の暑熱ストレス回避技術として、空調設備の導入、換気扇等による強制換気、遮光ネット等による遮光等が試行されているが、大きなコストを要する。一方、我々の技術では既存設備下で、動物の生育・体調維持に繋がり、前記コスト面での問題は解消できるものと考える。また、当該藍藻は栄養的にもタンパク質・脂質含有量が他の藍藻類に比べて多い。また、当該藍藻はそれ自体が顕著な高温耐性を有するため、高温下でも培養破綻が起きにくく、他の藍藻類よりも安定した供給が可能である。
新技術の特徴
・当該藍藻を含む飼料の摂取により、暑熱区飼育のカエル(変温動物)の高温耐性能が向上、また暑熱区飼育のニワトリ(恒温動物)の暑熱ストレスが減少
・少ない配合量で顕著な効果を発揮(ニワトリの場合)
・培養から製品化までのプロセスが低エネルギーかつカーボンニュートラル
想定される用途
・夏季高温時、畜産動物の食欲促進用飼料
・愛玩動物の食欲促進用飼料
関連情報
サンプルあり
- 14:30~14:55
- 材料
広島大学 大学院先進理工系科学研究科 応用化学プログラム 助教 湊 拓生
新技術の概要
従来の水熱合成や固相合成などの酸化物合成手法では、前駆体構造を保持することができないため、最終生成物の構造や露出面を制御することは極めて困難であった。本技術は前駆体の構造を保持したまま次元性を逐次的に増加させる新規合成手法であるため、従来法では困難であった準安定なα-MoO3を合成することに成功した。
従来技術・競合技術との比較
従来のα-MoO3合成手法では熱力学的に安定な(010)面が主に露出するため、触媒反応活性に乏しく、また比表面積も小さい。本手法で合成したα-MoO3はルイス酸点が豊富な(100)面が主に露出しており、かつ比表面積も大きい(>30 m2/g)ため、優れた酸触媒活性を示す。
新技術の特徴
・グラムスケール合成可能
・高比表面積
・(100)面の露出
想定される用途
・参照試薬としての販売
・触媒
・電極材料
関連情報
サンプルあり
- 15:00~15:25
- 医療・福祉
4)脳生体ダイナミクスを捉える摂食嚥下機能リモート評価訓練システムの開発
発表資料広島大学 脳・こころ・感性科学研究センター 特任准教授 濱 聖司
新技術の概要
嚥下は反射・随意運動と認知機能が複雑に関連して診断と訓練が行える施設が限られる。末梢交感神経を血管のかたさ(末梢血管剛性)で評価する独自のシーズ技術により、水蒸気のネブライザーでも喉頭感覚の評価と嚥下訓練が可能となり、水飲み動作と認知機能課題を組み合わせることによって嚥下障害の推定を可能とした。また、起立台と組み合わせて30度挙上という低負荷試験でも自律神経活動が評価でき、訓練に応用できることも確認した。
従来技術・競合技術との比較
不顕性誤嚥と嚥下機能の評価は侵襲的で特殊な機器を使う嚥下造影検査と嚥下内視鏡検査が一般的。嚥下音だけのウエアラブル検査装置は不顕性誤嚥の評価が困難であり、咳テストは認知機能や自律神経は評価できない。
新技術の特徴
・認知・運動・嚥下機能を自律神経活動の変化から非侵襲的に評価(見える化)できる
・家庭や施設など専門家不在の状況でも、摂食・嚥下機能と認知機能を調べて訓練できる可能性がある
・ネブライザー(吸入器)と起立台(ヘッドアップチルト)の侵襲性を低減して対象者を拡大できる可能性がある
想定される用途
・外来や入院で摂食・嚥下障害に対して評価と訓練をする時に使用
・入院してリハビリを行って何とか飲み込めるようになった嚥下機能を自宅や施設で維持したい
・嚥下機能や認知機能が気になって、自宅や施設で調べて、少し訓練もしたい時
- 15:30~15:55
- アグリ・バイオ
広島大学 大学院統合生命科学研究科 生物工学プログラム 准教授 青井 議輝
新技術の概要
本技術は、ゲルマイクロドロップレットを活用し、難培養微生物の資源化する革新的スクリーニング手法である。具体的には、難培養微生物を可培養化する新規培養技術と、10⁸個という膨大なサンプル数から目的活性を有する微生物を評価・選別する、ハイスループットスクリーニング手法を組み合わせることで実現する。
従来技術・競合技術との比較
従来の分離培養技術では環境微生物のうち1%程度しか培養できないが、本手法では50%という微生物学の常識を覆す割合の微生物が可培養化される。また、従来のドロップレット培養技術では、培養菌体の活性や機能評価は極めて困難であったが、本技術では、多様な機能を対象に評価することを可能にする。
新技術の特徴
・10⁸個という極めて多数の独立した培養系の機能評価が可能
・新規酵素、化合物変換活性、特定物質生産活性、抗菌活性、特定遺伝子阻害活性など多様な評価に対応可能
・従来法では培養できない未培養・難培養微生物も評価・利用可能
想定される用途
・未培養・難培養微生物の資源化(創薬資源)
・未培養・難培養微生物の資源化(農業・食品・化学分野)
・変異株ライブラリーを用いた超高速スクリーニング
関連情報
展示品あり
お問い合わせ
連携・ライセンスについて
広島大学 産学連携部
TEL:082-424-4302
Mail:techrd hiroshima-u.ac.jp
hiroshima-u.ac.jp
URL:https://www.hiroshima-u.ac.jp/
新技術説明会について
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町
TEL:03-5214-7519
Mail:scett jst.go.jp
jst.go.jp