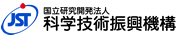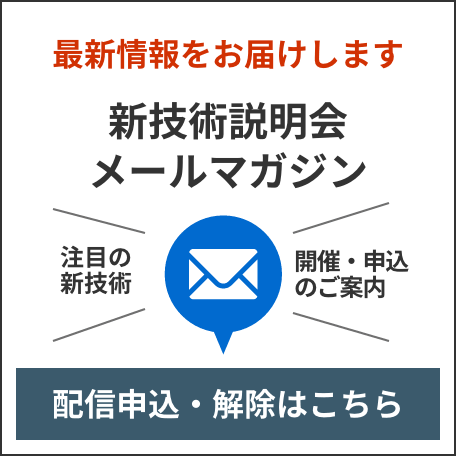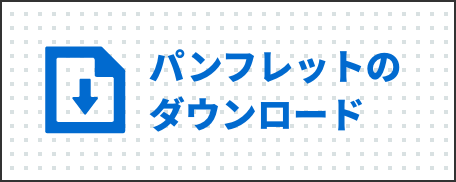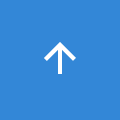JST研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)①~ICT、電子デバイス、ものづくり、機能材料、アグリ・バイオ~ 新技術説明会【オンライン開催】
日時:2025年11月13日(木) 13:00~15:55
会場:オンライン開催
参加費:無料
主催:科学技術振興機構
発表内容一覧
発表内容詳細
- 13:00~13:25
- 医療・福祉
1)生体模倣による設計自在で繰り返し吸収可能な薄型衝撃吸収材
北海道大学 大学院工学研究院 機械・宇宙航空工学部門 准教授 山田 悟史
新技術の概要
力学的に最適化された骨構造を模倣した「海綿骨模倣構造」を採用し、柔軟で復元性に優れたTPU素材を用いることで、あらゆる方向の衝撃を効果的に吸収し、繰り返しの衝撃にも耐える優れた衝撃吸収材を実現。生体適合性と通気性も兼ね備える。身体保護材のほか、形状や性能を自在に設計できることから幅広い応用が期待される。
従来技術・競合技術との比較
一般的な衝撃吸収材である発泡スチロールと比較して、同等以上の衝撃を繰り返し吸収でき、薄型化も可能。3Dプリント性・生体適合性・通気性を備えているため、個人に合わせたパーソナライズ設計が容易。従来の多孔質構造と比べて3次元等方性に優れ、設計自由度が高いため、性能の分布や異方性の制御も可能。
新技術の特徴
・3Dプリント可能で設計自由度が高く、パーソナライズ設計が容易
・あらゆる方向からの繰り返しの衝撃を効果的に吸収
・TPUに限らず他の樹脂や金属3Dプリントにも展開可能
想定される用途
・ヘルメットやヒップパッド内部の衝撃吸収材
・靴のソールやインソール
・輸送用緩衝材
関連情報
サンプルあり
- 13:30~13:55
- 計測
2)低騒音プロペラ開発のための3次元旋回流相対速度計測システム
摂南大学 理工学部 機械工学科 教授 堀江 昌朗
新技術の概要
回転体相対静止撮影技術をステレオ撮影法に応用し、高速旋回流を低速な三次元相対流れとして計測可能な革新的画像流速計測システムの開発を目指しています。高速回転する翼により生ずる渦やキャビテーションを正確に可視化し、騒音や振動を効果的に抑制することで、高性能な流体機械の開発や実用化に大きく貢献します。
従来技術・競合技術との比較
従来の計測手法では高速旋回流の撮影にブレが生じ、周速度を除いた三次元速度場を正確に把握することは困難でした。数値解析に頼らざるを得ず、実際の現象を十分再現できない点が課題でした。本技術により相対速度を高精度に計測することが可能となり、流体機械の信頼性向上や効率改善に貢献します。
新技術の特徴
・回転体相対静止撮影技術を応用したステレオ撮影により、高速旋回流を低速な三次元相対流れとして精密に可視化できる
・撮影時のブレや解析精度を向上させ、渦やキャビテーションの挙動など実際の流動現象を正確に捉えることが可能
・騒音や振動の低減に直結し、タービン・ポンプ・ドローン等の信頼性や効率向上に大きく貢献
想定される用途
・タービンや風車の渦・キャビテーション挙動を把握し、騒音・振動を抑制して高効率化に貢献
・水中ポンプや送風機での流動状態を正確に解析し、故障リスクを低減し長寿命化に貢献
・大型ドローンやフライングカーのプロペラの安全性と静粛性の向上に貢献
関連情報
デモあり
展示品あり
- 14:00~14:25
- 材料
3)静電気が見える!革新的、静電気発光センサ・センシング
産業技術総合研究所 センシング技術研究部門 製造センシング研究グループ
研究グループ長 寺崎 正
新技術の概要
本技術は、「世界初!の静電気発光(SEL)材料」であり、「静電気を、目視・カメラで見られる、唯一の技術」です。静電気・帯電の場所や電位変化に応じた輝度の発光が観測されるので、帯電や除電を直感的に理解できます。SEL材料入りの塗料を塗布して使うため、移動体、3D曲面での計測が可能で、無意識の帯電を理解できます。
従来技術・競合技術との比較
従来技術と比較して、静電気発光(SEL)は、下記の強みを有します。
■静電気を、目視・カメラで見られる、唯一の技術
■センサが塗料の為、移動体、3D曲面での計測が可能
■発光の面分布から、無意識の帯電を捉える事が可能
新技術の特徴
・静電気発光(SEL)は、静電気を、目視・カメラで見られる、唯一の技術
・静電気発光の輝度と分布から、静電気の【帯電量(>1kV)】と【範囲】が分かります
・SELセンサ活用し、表面伝導率領域、つまり除電経路を選択的に可視化可能
想定される用途
・除電経路が見える事による、除電設計の最適化(対策は正しいか)
・帯電が見える事による、帯電現象の究明(どこで発生し、不具合に至るか)
・製造現場等での、静電気リアルタイム監視 (無意識の帯電に気付けるか)
関連情報
サンプルあり
デモあり
展示品あり
- 14:30~14:55
- 材料
4)世界最高性能の近赤外反射遮熱膜
名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授 長田 実
新技術の概要
酸化タングステンをベースとする透明導電体ナノシートを合成し、膜厚50 nmの超薄膜において世界最高レベルの近赤外反射率54%と遮熱効果を示す近赤外遮蔽膜の開発に成功しました。本研究で開発した近赤外遮蔽膜は、優れた遮熱効果と可視光透明性を併せ持っており、建築物、自動車の高性能エコガラスへの応用が期待されます。
従来技術・競合技術との比較
従来の薄膜プロセスでは、真空製膜装置や高価な装置が利用されてきましたが、我々の技術では、安価で簡便な室温・水溶液プロセスにより、ガラス、シリコン、金属、プラスチックなど様々な基材への遮熱膜コーティングが可能です。
新技術の特徴
・酸化タングステンをベースとする透明導電体ナノシート
・世界最高レベルの近赤外反射率54%と遮熱効果を実現
・安価で簡便な室温・水溶液プロセスによりコーティングが可能
想定される用途
・近赤外反射遮熱膜
・エコガラス
・透明導電体膜
関連情報
デモあり
- 15:00~15:25
- 材料
5)有機・無機のナノ複合化で自己修復ハイブリッドガラスを開発
山形大学 大学院有機材料システム研究科 有機材料システム専攻 教授 森 秀晴
新技術の概要
硬い無機材料であるガラスは透明性や耐薬品性等に優れた特性を持つが靭性が低く一般に修復機能はない。本研究では、シルセスキオキサン微粒子を基盤とした有機と無機のナノ複合化技術により、通常トレードオフの関係にある自己修復能力と材料の硬さや力学物性を併せ持つガラス状の自己修復ハイブリッドを開発した。
従来技術・競合技術との比較
高分子鎖は組織内部で活発に熱運動をしており、破断面の間で高分子鎖が互いに相互貫入して絡み合い自己修復を促す。一方、ガラスは熱運動性が著しく遅いため自己修復しない。材料として必須となる硬さや耐擦傷性と自己修復機能はトレードオフの関係であり、透明で高強度な自己修復材料の開発は困難であった。
新技術の特徴
・基本骨格がSi-O結合であるシルセスキオキサン微粒子の特徴によってトレードオフの関係にある自己修復能力と材料の力学物性の同時獲得を実現
・分子設計の自由度が高く、有機・無機の構造/組成/サイズにより、ヤング率、透明性、耐熱性、自己修復性などの性能・機能を任意に制御可能
・基盤となるシルセスキオキサンは比較的簡便で温和な条件下で合成することが可能であり、溶解性・分散性に優れる
想定される用途
・自己修復ハイブリッドガラス
・自己修復ハードコート材料
・塗料/接着剤/光学材料などへの自己修復性を付与する添加剤
- 15:30~15:55
- 創薬
6)マイクロフロー合成法による、低廃棄物量、低コスト、迅速ペプチド合成
名古屋大学 大学院創薬科学研究科 基盤創薬学専攻 教授 布施 新一郎
新技術の概要
旧来のフラスコや反応釜を用いるバッチ合成法と異なる、微小な流路を反応場とするマイクロフロー合成法について紹介する。マイクロフロー合成法は高速混合、反応場の比表面積の高さから反応時間と温度を厳密に制御できる。本説明会では、この特長を活かしたペプチドの高効率合成の開発について発表する。
従来技術・競合技術との比較
ペプチドの汎用的化学合成法では、競合する副反応を回避するため、廃棄物量が多く、高価な反応剤を用いている。一方で、開発手法では、安価で低廃棄物量の高活性反応剤を用いつつも、マイクロフロー合成法の特長を活かすことで、副反応の回避に成功している。
新技術の特徴
・旧来のフラスコ、反応釜と異なる微小流路を反応場とする有機合成法
・精密な反応温度・時間制御により安価な反応剤を用いつつ副反応を抑制
・低廃棄物量、低コスト、迅速ペプチド合成の実現
想定される用途
・医薬品生産
・農薬生産
お問い合わせ
連携・ライセンスについて
科学技術振興機構 スタートアップ・技術移転推進部 研究支援グループ
TEL:03-5214-8994
Mail:a-step jst.go.jp
jst.go.jp
URL:https://www.jst.go.jp/a-step/
新技術説明会について
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町
TEL:03-5214-7519
Mail:scett jst.go.jp
jst.go.jp