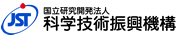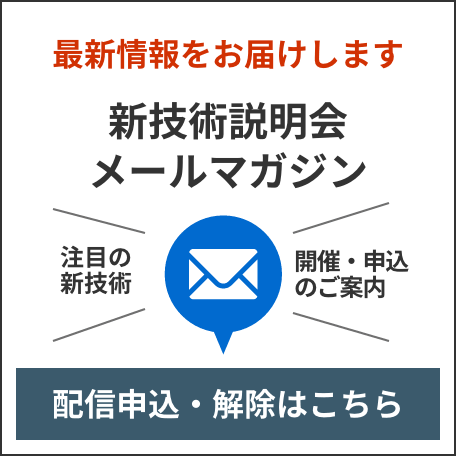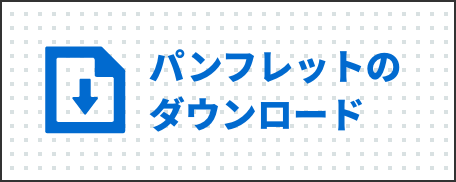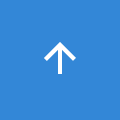明治大学 新技術説明会【オンライン開催】
日時:2025年12月02日(火) 10:00~11:55
会場:オンライン
参加費:無料
主催:科学技術振興機構、明治大学
発表内容一覧
発表内容詳細
- 10:00~10:25
- アグリ・バイオ
1)ジャスモン酸とストリゴラクトンによる根寄生雑草の相乗的自殺発芽誘導
明治大学 農学部 農芸化学科 専任准教授 瀬戸 義哉
新技術の概要
根寄生雑草はこれまで宿主の根から分泌されるストリゴラクトンを認識して発芽することが知られており、この性質に基づいた自殺発芽誘導法が考案されてきた。今回の技術では、ストリゴラクトンとジャスモン酸を混合することにより、発芽誘導活性が相乗的に増強することを見出した。
従来技術・競合技術との比較
これまでは、ストリゴラクトンを単独で使用した自殺発芽誘導法が考案され、その効果が実証されてきたが、本技術においては、これにジャスモン酸を添加することで、活性を顕著に高められることを見出した。特に、市販農薬の一種が利用可能であることも見出しており、自殺発芽誘導の実用化を促進する技術である。
新技術の特徴
・ジャスモン酸とストリゴラクトンを混合することで、相乗的に根寄生雑草の発芽を誘導することができる
・さまざまなジャスモン酸類が相乗効果を発揮することに加え、市販農薬であるジャスモメートも強力な相乗効果を発揮する
・根寄生雑草の種類によっては、ジャスモン酸類の単独投与でも、比較的強力な効果を発揮する
想定される用途
・ジャスモン酸とストリゴラクトンの併用によるストライガに対する自殺発芽誘導剤
・ジャスモン酸の単独投与による、ヤセウツボに対する自殺発芽誘導剤
- 10:30~10:55
- 情報
2)フィジカルAIで自律走行ロボットを身近にする
明治大学 総合数理学部 ネットワークデザイン学科 専任教授 森岡 一幸
新技術の概要
深層強化学習と走行可能領域検出の2つのAIを用いて、自律走行ロボットを実現する。実環境での計測における外乱の影響を低減し、仮想環境で学習したAIモデルを実機に適用できるようにした。人間が大まかな目的地の方向へ目で見て歩行できる場所を歩いていくのと同様の仕組みで、未知の場所でも走行できる性能を持つ。
従来技術・競合技術との比較
従来の自律移動ロボットは、行動エリアの壁や障害物等の位置や構造を記録したロボット用の地図を事前に作成し、厳密に地図に基づいて走行するので、未知の環境や歩行者が多いような環境では使えない。本技術は、そのような事前準備は必要なく、動的な障害物にも適応できる。高価なセンサを使用しない構成でも実現できる。
新技術の特徴
・End to Endモデルを用いるので、入力するセンサに合わせてモデルを学習することができる・・・単眼カメラのような安価なセンサ入力でも適切に行動できるモデルが作れる → 圧倒的に安価に自律移動ロボットが開発できる
・事前に詳細なロボット用の地図を準備する必要はない・・・未知の環境でも使えるロボット → ポータブルなロボットシステムが実現できる
・歩行者が多い環境でも動作する学習モデルが作れる・・・前方の歩行者に追従したり、向かってくる歩行者を回避したりも、同じAIの枠組みで実現可能
想定される用途
・短期間でも運用できる自律運搬ロボット・・・事前の地図作成コストが無いのでイベント会場等の短時間の運用でも容易に使用できる
・AI適用によるロボットサービスのPoCのコスト低減・・・ロボットサービスへの参入を検討する企業等が、AI導入だけで低開発コストでPoCができる
・自律移動ロボットサービスの大規模運用・・・従来のロボットよりもロボット開発コストは圧倒的に下がるので、大規模展開の可能性が向上する
関連情報
・サンプルあり
・デモあり
- 11:00~11:25
- 医療・福祉
3)パーキンソン病患者の歩行を改善する小脳リズム刺激装置
明治大学 理工学部 電気電子生命学科 専任教授 小野 弓絵
新技術の概要
一定のリズムに運動が同期する「位相引き込み現象」を活用し、正弦波状交流電流を小脳へ与えてパーキンソン病患者の歩行機能を改善する技術。歩行リズムが常に一定でない患者にも適応した刺激法を導入し、非侵襲・非薬物的に生活で実感できるレベルの機能改善を実現している。
従来技術・競合技術との比較
従来の薬物治療は歩行機能への効果は小さく、脳深部刺激療法は著効するが外科手術が必要であった。非薬物治療として視聴覚キューや歩行支援ロボットなども提案されてきているが、歩行周期にリアルタイムで適応するクローズドループ型のリハビリテーション機器はこれまでになく、本技術の独自な特長となっている。
新技術の特徴
・非薬物、非侵襲のパーキンソン病症状緩和を実現
・デイサービス、健康事業などにおける自動化された歩行促進プログラムとしての活用
・スマートフォンベースの在宅治療用SaMDへの期待
想定される用途
・在宅やデイケアでのテーラーメイド・リハビリテーション
・定期的な入院リハビリテーションにおける集中訓練
・在宅治療による日常生活動作機能の向上、社会参加の促進
関連情報
・サンプルあり
・デモあり
- 11:30~11:55
- デバイス・装置
4)あらゆる味を再現するディスプレイ、映像からも味を推定
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 専任教授 宮下 芳明
新技術の概要
味や香料を混合してあらゆる味を再現するディスプレイを発表していますが、映像からのAI推定で味を直接測定しなくても味を推定でき、推定結果を映像データの中に含めておけるので、テレビを見ながら味わいたいものをタップするだけで「味見」をすることができるようになりました。白黒映像やアニメであっても動作します。
従来技術・競合技術との比較
味センサによる測定でデータ化する場合は、その飲食物自体を用意する必要がありましたが、本技術はそれが不要なので、過去の映像や写真さえあれば推定可能です。
新技術の特徴
・あらゆる映像に映る飲食物が「味見可能」になります
・推定された味情報を映像データに含めることができます
想定される用途
・テレビで映っているものが味見可能になります
・数十年前の映像資料さえあればその飲食物の味を推定して味わえます
・スマートフォンで撮った映像やSNSにアップされた動画を味わうこともできます
お問い合わせ
連携・ライセンスについて
明治大学 研究推進部 生田研究知財事務室
TEL:044-934-7639
Mail:tlo-ikuta  mics.meiji.ac.jp
mics.meiji.ac.jp
URL:https://www.meiji.ac.jp/tlo/collaboration_menu.html
新技術説明会について
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町
TEL:03-5214-7519
Mail:scett jst.go.jp
jst.go.jp